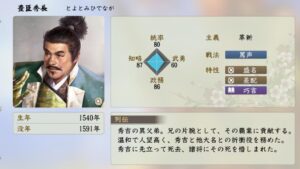Netflixシリーズ「ミスター・サンシャイン」独占配信中 韓国メディアは先日、1人の独立運動家の遺骸が100年ぶりにアメリカから帰国し、大々的な「奉還式」が行われたと一斉に報道した。式に合わせて開かれたシンポジウムのテーマは「独立した祖国でまた会いましょう(See you again)」。 Netfrixで配信中のドラマ『ミスター・サンシャイン』(2018、全24話)のラストで、ヒロインのエシン(キム・テリ)が発するセリフである。ドラマの人気とともに一時期韓国でも流行したフレーズが、なぜまた再び登場したのだろう? 実は、100年ぶりに祖国に帰還した人物とは、ドラマでイ・ビョンホンが演じた主人公ユジン・チョイのモデルになったとされる、「ファン・ギファン」だったのだ。 韓国では1948年の建国以来、日本の植民地支配からの独立に貢献したとされる人物を発掘し、国家が表彰する制度(独立有貢表彰者)を設けている。毎年、1人でも多くの独立貢献者を探そうと躍起になった政府は、少しでも痕跡があれば表彰者にリストアップしてきたのだが、1995年の新聞の一面をびっしりと埋め尽くすリストの中に、ファン・ギファンも混ざっていた。 2018年、『ミスター・サンシャイン』が大ヒットした際、ユジン・チョイにモデルはいないと製作者は主張したものの、ネットを中心に多くの視聴者がモデル探しを始め、政府にまでその要請が広まってファン・ギファンにたどり着いたというわけだ。ファンの墓は2008年に発見されていたが、ドラマの放送で注目されたことで、同年に100年目の奉還の話が本格化したという。 今回のコラムでは、ファン・ギファンが本当にユジン・チョイのモデルと言えるかの真偽も含め、『ミスター・サンシャイン』が背景にしている歴史を、ドラマと史実を照らし合わせながら辿ってみたい。それによって、韓国社会が持ち続けている「なかったことへの欲望=歴史に対するフェティシズム」が見えてくるのではないかと思う。 イ・ビョンホン演じるユジン・チョイ。 Netflixシリーズ「ミスター・サンシャイン」独占配信中 スター俳優2人のラブストーリーを盛り上げる「愛国心」 全24話から成る『ミスター・サンシャイン』の始まりは1871年まで遡る。 この年、かつてアメリカが日本に対してそうしたように、朝鮮に対しても開港を要求、軍艦を先頭に攻撃するという、「辛未洋擾(辛未の年の1871年に、西洋=アメリカによって起こった乱の意)」が起こった。その混乱の最中、アメリカ人宣教師の助けで渡米した賤民の子どもが、やがて米軍の将校となり朝鮮に帰ってきてから繰り広げられる出来事がドラマの中心となっている。 ドラマが舞台としているのは、ちょうど大韓帝国(1897-1910)の時代と重なっていて、この時期に日清戦争、日露戦争で勝利を治めたことで朝鮮半島の支配力を独占しようとしていた日本に対する抵抗が、必然的に物語の軸となってくる。 もちろんドラマ自体は、ユジン・チョイとエシンのラブストーリーが中心となっており、歴史は2人の恋を翻弄する「装置」として働いているに過ぎない。イ・ビョンホンとキム・テリというスター俳優によって演じられる美しくも壮絶な愛は、大韓帝国が日本に踏みにじられれば踏みにじられるほど、「愛国心」を際立たせていく。 視聴者もまた、2人の愛に感情移入しつつ、愛国心を掻き立てられて最後まで目を離さずにはいられない。しかも敵が「侵略者」である日本ならなおのこと。本作が有料のケーブルチャンネルで放送されたにもかかわらず高視聴率を記録したのは、本作がいわゆる「クッポン(국뽕)=愛国心+ヒロポンの造語で、過剰に愛国心を煽ることを皮肉った表現」であることも一役買ったかもしれない。 そして、歴史に対するフェティシズムを如実に表す言葉といえば、「クッポン」の他にないのだ。 清、ロシア、日本を引き入れ、朝鮮を滅亡に導いた権力者たち では、そもそも大韓帝国とはどのように成立し、どのような国だったのだろうか? 「大韓帝国」は、1897年から1910年の間、13年という短い間に朝鮮半島に存在した国家である。と言っても、実際は「朝鮮」が国名を変えただけの、名ばかりの国に過ぎなかった。当時の王、高宗(コジョン)はなぜ「朝鮮」から「大韓帝国」へと国名を変えるに至ったのだろうか。 それを知るためには、高宗の妻「閔妃(ミンビ、王妃の閔氏)」の存在を避けては通れない。なぜなら、彼女こそがすべての発端と言っても過言ではないからだ。 「朝鮮」末期、権力は閔妃一族が握っていた。一族は朝廷の要職を掌握、金銭や財物をもらって官職を売る「売官売職」から税金の着服まで、あらゆる不正を働き、国全体が腐敗の修羅場と化していた。 中でも一族の首長、閔妃の浪費癖は国庫を潰すほどだったと言われており、「宮廷で毎晩宴会を開き、歌手や雑技を見せる者に与えた金品は数え切れないほど莫大」「塗炭の苦しみに陥った民生は眼中になし」といった記録が数多く残る閔妃の悪行に対し、民衆は不満を募らせていた。 一族による腐敗政治や浪費の悪弊は軍にも及び、兵士たちは1年以上給料を払われず、やっと出た給料が半分は腐り、半分は砂だらけの米だったことから彼らの怒りが爆発、同調した民衆も加わった「壬午軍乱」(1882年)が起きたのである。 兵士と民衆は閔妃一族とその手下を次々と殺し、宮内にまで突撃して閔妃を処断しようとした。命からがら逃れた閔妃は、夫である高宗に密書を送り、清国に鎮圧のための出兵を要請してもらう。 閔妃はさらに、自らの政敵であった興宣(フンソン)大院君(高宗の父、つまり閔妃にとっては舅にあたる)まで排除しようとし、これに応じた清は興宣大院君を拉致、自国(清)に幽閉してしまう。 こうして閔妃は殺されずに済んだものの、朝鮮は清からさらなる内政干渉を受けるようになり、その上、日本軍の駐屯も認めざるを得なくなった。 日本軍は自国民の保護を建前の目的としながらも、実際は清をけん制し、朝鮮での支配力を広げることを企んでいた。閔妃一族は自らの権利欲と私利の結果、日清の軍隊を朝鮮に呼び寄せることとなり、朝鮮の運命を外部の勢力を意味する「外勢(외세、ウェセ)」に丸投げするという愚を犯したのである。 自力では何もできず、外勢に頼りっぱなしの閔妃ら朝鮮の権力者たちは、1894年に起こった東学党の乱(東学農民運動)の鎮圧にも清を頼り、清が出兵する際には自動的に日本軍も介入するという1885年の天津条約によって、朝鮮が日清戦争の主戦場になっていく下地を作った。 朝鮮の権力者たちは、これまで世界の中心と崇めてきた中国(清)が、日清戦争で日本に負ける姿を目の当たりにして大きな衝撃を受けるが、さらに日本が日清戦争の戦利品として獲得した遼東半島を、その後の「三国干渉」によって清に返還すると、閔妃は、今度はそれを主導した「強国」ロシアへとすり寄っていくようになる。 キム・テリ演じるエシン。 Netflixシリーズ「ミスター・サンシャイン」独占配信中 ナショナリズムを煽る「悲劇のヒロイン」となった閔妃 朝鮮を植民地にし、大陸進出への足掛かりとしたい日本にとって、閔妃が邪魔な存在だったことは言うまでもない。 日本は公使館員や軍、浪人らを総動員して閔妃暗殺を実行した「乙末事変」(1895年)、こうして閔妃は、あたかも日本によって悲惨な死を遂げた悲劇のヒロインとして歴史に形作られていくことになる。 だが、それによって生前の彼女の悪政が隠蔽されてしまってよいのだろうか。 彼女は今やナショナリズムを煽る英雄として、ドラマや映画、ミュージカルにまでなってことごとく美化されている。「閔妃」という名前は日本側がつけた貶められた呼び名だとして、大韓「帝国」にふさわしい「明成(ミョンソン)皇后」こそが正しい名だと主張する人々も多い。 こうして彼女が朝鮮を滅亡への道に導いたという事実は見えなくなり、閔妃の死を正当化するために、日本はますます悪なる存在としてステレオタイプ化されていく。 閔妃の死をめぐっては、いまだ日韓で多くの研究が行われていて、殺害の現場には朝鮮軍もいたこと、焼却した遺骸を埋めたのが朝鮮軍であることからも、彼女を殺したかったのが日本軍だけではないことが明らかになっているが、都合の悪い歴史が明るみに出ることはない。 余談だが、焼かれた閔妃の死体を埋めた人物はウ・ボムソンという朝鮮軍の指揮官だった。彼はその後、大韓帝国に忠誠を誓う保守派たちに命を狙われて日本に亡命し、日本政府の庇護のもと日本人と結婚、その子供はやがて日本政府の支援で農学博士となり、種のないスイカを開発して世界を驚かせた。 韓国で知らない人はなく、ノーベル賞を取っていたかもしれない人物として国民が尊敬してやまない「ウ・ジャンチュン博士」である。 だが、この博士がウ・ボムソンの息子だと、一体どれだけの人が知っているだろうか。韓国では、かつて日本に協力した「親日派」は、親日派事典にその名を刻まれ、末代まで蔑みの対象となる扱いを受ける。 閔妃を英雄にするならば、閔妃の死に加担したウ・ボムソンは民族の敵であり、その息子ウ・ジャンチュンも同じく許されない存在になる。 にもかかわらず、立派な功績を遺した彼もまた韓国の英雄にすべきであるとして、不都合な事実は隠蔽され、都合の良い部分だけが切り取られて物語となっていく。 さて、妻が殺される瞬間、間近で恐怖に慄いていた高宗は、閔妃暗殺から1年後にロシア公使館に逃げ込む事態(俄館播遷)となる。 国のトップが外国の公使館に逃げるという、朝鮮にとっては屈辱的なこの出来事から1年後、高宗が王宮に戻り、宣布したのが「大韓帝国」であった。 その背景には、朝鮮の清からの独立を目論む日本の戦略だったという説なども飛び交い、少なくとも清と同等の立場になることで独立の意志を見せようとしたことは確かだが、この時点での朝鮮の国力は最悪であった。 建国に至るまでの経緯があまりにも酷いことからも想像できるように、大韓帝国は近代化や国力の立て直しとは逆行する「皇権強化」を打ち出した。 […]
「こうあって欲しかった歴史」への欲望 ドラマ「ミスター・サンシャイン」とクッポン