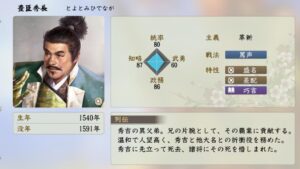名古屋のシンボル金鯱。言わずと知れた、徳川家康が築かせた名古屋城の天守の最上部で輝いているあれだ。展覧会で地上に降りた姿を目にした方も多いことだろう。じつは金鯱には東アジアにおいて長い歴史があった。金鯱ほど目立たないが、反り返った魚のような形の飾りが日本中の寺院や宮殿の屋根の両端に載っている。なぜあの形なのか。いつから載っているのか。城郭考古学が専門の研究者で、『歴史を読み解く城歩き』(朝日新書)を出版したばかりの、千田嘉博・奈良大学教授がその歴史を明かしている。長年、歴史や文化財を取材してきた朝日新聞の塚本和人さんが、千田氏の説の概要と、遠くモンゴルの草原の墓でみつかった壁画のレポートなども合わせ、日本と東アジアのダイナミックな金鯱のつながりを紹介する。 ■金鯱、東京国立博物館に降臨 2022年秋、東京国立博物館の創立150年を記念する特別展「国宝 東京国立博物館のすべて」(2022年10月18日~12月18日)が開催されました。同館が所蔵する国宝89件のすべてが公開されると話題を集めた同展覧会の会場一角に、名古屋城の天守を飾る金鯱(実物大レプリカ)が展示されました。 明治5(1872)年、文部省博物局による日本初の官設博覧会が湯島聖堂を会場に開かれました。これが、現在の東京国立博物館の始まりとされています。この博覧会で多くの観覧者を魅了したのが名古屋城の天守からおろされた金鯱でした。金鯱は1873年にウィーンで開かれた万国博覧会にも出陳され、世界に日本の文化財の魅力を伝えることに貢献したのです。その後、金鯱は名古屋城の天守に戻ったのですが、1945年の空襲で城と一緒に失われてしまいました。戦後、名古屋市の復興のシンボルとして大天守が再建され、金鯱もともによみがえりました。 その名古屋城の金鯱が誕生するまでの長い物語が、千田嘉博「金鯱の歴史的意義」(『名古屋城金シャチ特別展覧 公式ガイドブック』名古屋城金シャチ特別展覧実行委員会、2021年)に記されています。 ■7世紀のモンゴルにもあった鴟尾 千田さんはまず鯱の源流をさかのぼります。鯱とは、頭が龍(虎とも)、胴は魚、背中に尖ったひれをもつ空想の生きものです。 古代中国では宮殿や霊廟の屋根に「正吻(せいふん)」と呼ばれる棟飾が備えられ、そのモチーフは龍とみられています。龍は古くから中国を中心とする東アジア世界では「最高位の吉祥文」であり、「天界を自在に駆け昇り、雨を降らせ、霊力をもった霊獣としての龍は、皇帝をはじめとした権威の象徴になった」とされてきました。龍のモチーフは、すでに弥生時代の日本列島にも伝わっていたと考えられていますが、そうした中国で成立した棟飾は飛鳥~奈良時代には宮殿・寺院の「鴟尾(しび)」としてとりいれられました。 鴟尾が伝わったのは日本だけではありませんでした。同じころのモンゴルにも鴟尾が伝わっていたことが、2011年、モンゴルの首都ウランバートルの西方約220キロにある草原でみつかった地下墓(オラーン・ヘレム墓)の発掘調査で明らかになりました。その墓は7世紀につくられたとみられ、地下道の壁面には、モンゴル初となる極彩色壁画が描かれていたのです。奈良県明日香村の高松塚古墳やキトラ古墳の石室にも表現されていた「青龍」と「白虎」のほかに「樹下人物図」などの複数の人物や動物の図もありましたが、注目されるのは朱色に塗られた「楼門図」で、瓦葺きの建物の屋根に、立派な鴟尾が表現されていたのです。 地下墓がみつかった地域は、トルコ系騎馬遊牧民の突厥(とっけつ)が6世紀半ばごろから支配してきたのですが、630年に唐王朝に服属し、唐の間接統治を受けることになりました。壁画が描かれたのは、突厥が唐の間接統治を受けたころとみられ、唐の文化が草原地域にも浸透していたことを示しています。 その後も日本は東アジア世界との交流を続け、その過程で鯱の原形も伝わってきたとみられます。それを示す例として、千田さんは16世紀前半に仇英が描いたとされる中国の都市図・風俗図「清明上河図」を挙げ、描かれている城壁の楼門や宮殿、邸宅などの屋根の多数の棟飾(正吻)に注目しました。日本の城の屋根に鯱があげられていく直前に、中国では龍をモチーフとした棟飾が広く使われ、シンボルとして明快な意味を持ち、それが東アジア世界に影響を与えたのではないかと指摘しています。 ■いつから天主に載るようになったのか? それでは、日本の城でどのように鯱が誕生したのか。これまで城の天主は、織田信長が1576年から建設を始めた安土城(滋賀県近江八幡市)で出現したとされてきました。千田さんはその理解に修正が必要なことを実証的に明らかにしています。 明智光秀が1571年に坂本城(大津市)の築城を始めたころ、京都の吉田神社の宮司で、光秀とも交流があった公家の吉田兼見が坂本城の建築現場を訪れ、その日記に「天主以下をことごとく見た」と記しています。また、1573年に細川藤孝が勝龍寺城(京都府長岡京市)で連歌会を開いたとき、連歌師の里村紹巴が「天主で連歌・連句を二人で付けあって詠んだ」と記しています。この二つの城をめぐるエピソードからは、安土城よりも前に天主が成立していたと読み取れます。 同じ時期、畿内の城郭では巨大な木造の櫓を建てる建築技術も発展していました。松永久秀の多聞城(奈良市)について、興福寺多聞院の院主による『多聞院日記』は、1577年に奈良中から人夫を出して多聞城にあった「四階櫓」を破壊したと記しています。この日記からは、天主ではない、軍事的な巨大な櫓が畿内で出現していたことが分かります。千田さんは坂本城や勝龍寺城でみられた「天主」と多聞城で見られた「四階櫓」に注目し、「信長の安土城天主は、この両方を融合し、規模を圧倒的に拡大した上で、階層的な城郭構造の頂点に置き、政治と軍事を統合した信長政権の権威の象徴として創出した新たな『天主』であった」と読み解きました。 さらに、安土城の天主に葺かれたとみられる瓦についても考察しています。『信長公記』によれば、中国人の一観に瓦のデザインを担当させ、それを中国風にするように命じたそうです。千田さんは、このときに一観が鯱瓦を創出したのではないかとみています。一観が鯱に込めた思いとは何か。千田さんはこう考えました。「安土城天主は鯱が加わることによって、天主がただ城の頂点にそびえたというだけではなく、龍から昇華した霊獣・鯱が天主の大棟に舞い降り、また駆け昇る文化的象徴性を備えた特別な建物になった。それは信長がつくろうとした来たるべき社会のシンボルでもあった」 ■信長の中国文化を意識したデザイン、家康に受け継がれる 信長は、安土城天主内部の座敷群についても、当時の文化的価値観であった中国文化を頂点とした世界観で構成したとされます。千田さんは、そうした天主内観と表裏一体となった天主外観の象徴として、一観の助言を得た信長が、中国の正吻の文化的意義を踏まえた上で、独自の鯱瓦を創造したのではないかと想定しています。「最上階のさらに上にそびえた天主の大棟には、一対の鯱が尾を跳ね上げ、見晴るかす世界の安寧を守護した。天主の大棟に輝いた鯱は平和な世の将来を見る者に告げ、そして鯱を戴いた天主は、鯱によって天界と結ばれ、城も地域も鯱によって守護されることを約束した」 東アジアの伝統と文化に源流を持ち、信長の安土城天主から、江戸幕府を開いた徳川家康が受け継いで発展させた名古屋城の金鯱。その数奇な運命をたどってみると、ロシアによるウクライナ侵攻など未曽有の危機に直面している現在の私たちに、大切なことを訴えていると思います。 ■壁画の保存に日本の技術 最後に、オラーン・ヘレム墓の極彩色壁画のその後についてもお伝えしておきます。長さ8メートルに近い青龍と白虎などの壁画は、発掘直後からカビの発生などに襲われ、「存亡の危機」と言われるほどに劣化してしまいました。そこで、京都の文化財修復会社「彩色設計」の小野村勇人さんとスタッフの皆さんが、モンゴル側からの要請を受け、現地に数回赴いて、精密な壁画の模写や撮影などに取り組んできました。どんな文化財でも一度失われてしまうと、元には戻らないということ、だからこそ、大切に守らなければいけないということも、忘れてはいけないと思います。 千田嘉博さんの名古屋城の金鯱についての論考、「千田先生のお城探訪」(朝日新聞地域面連載中)を千田さんの最新刊『歴史を読み解く城歩き』(朝日新書)で読むことができます。新聞連載「千田先生のお城探訪」では、千田さんが国内各地とヨーロッパの城や城跡を実際に歩いてきた経験に基づき、考古学や文献史学などの知見を生かしながら歴史の真実に迫ります。書籍化にあたり、2019年10月から2022年9月までの記事をベースに、最新の知見が加筆されています。千田さんが撮影した各地のお城の美しい写真が満載です。 (塚本和人・朝日新聞東京本社イベント戦略室次長)
名古屋城・金のシャチホコはなぜあの形なのか? ルーツをたどることで明らかになった壮大な歴史とは