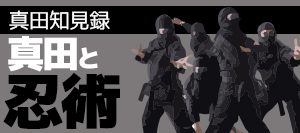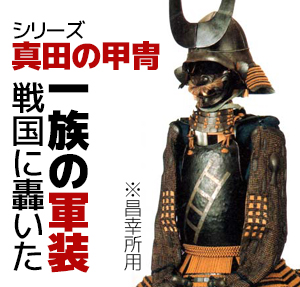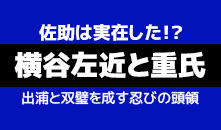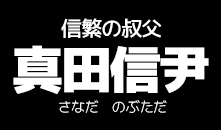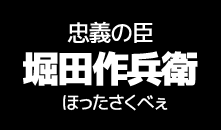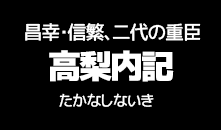武将列伝– category –
-
大谷吉治~幸村とともに戦った吉継の息子~
 一説には実弟とも伝わる、大谷吉継の子・大谷吉治。官位は大学助を叙任しており、史料によっては大谷大学などと記される場合もあります。(※その他、諱(いみな)に吉胤や吉勝など。) 真田幸村(信繁)は義理の兄にあたります。 慶長2年(1597年)に豊臣秀吉が大谷家を訪問した際(秀吉死去の前年)には、病状の悪化した父・吉継の代わりに...
一説には実弟とも伝わる、大谷吉継の子・大谷吉治。官位は大学助を叙任しており、史料によっては大谷大学などと記される場合もあります。(※その他、諱(いみな)に吉胤や吉勝など。) 真田幸村(信繁)は義理の兄にあたります。 慶長2年(1597年)に豊臣秀吉が大谷家を訪問した際(秀吉死去の前年)には、病状の悪化した父・吉継の代わりに... -
夜討ちの大将・塙団右衛門(ばんだんえもん)
 【江戸時代、軍記物や講談で民衆のヒーローに】 本来の名は、塙団右衛門直之。出身地や素性がはっきりとしない、まさに謎だらけの戦国武将。秀吉以来の豊富な軍資金を使って、全国の牢人衆をかき集めた豊臣家。まさにその牢人のイメージにぴったりの人物です。 ※余談ですが、浪人(ろうにん)はもともと、戸籍に登録された地を離れて他国を流...
【江戸時代、軍記物や講談で民衆のヒーローに】 本来の名は、塙団右衛門直之。出身地や素性がはっきりとしない、まさに謎だらけの戦国武将。秀吉以来の豊富な軍資金を使って、全国の牢人衆をかき集めた豊臣家。まさにその牢人のイメージにぴったりの人物です。 ※余談ですが、浪人(ろうにん)はもともと、戸籍に登録された地を離れて他国を流... -
織田有楽斎(長益)
 【覇王・織田信長の弟、栄華の時】 信長とは年齢が13歳離れた弟にあたる織田有楽斎。信長の存命時には長男・織田信忠の旗下にあり、信長が武田軍と対峙した甲州征伐などに従軍ました。 天正9年(1581年)の京都御馬揃えでは、信長の息子たち、信忠・信雄・信包・信孝・津田信澄の後に続いたとされ、信長御一門衆のひとりとして栄華を飾ったと...
【覇王・織田信長の弟、栄華の時】 信長とは年齢が13歳離れた弟にあたる織田有楽斎。信長の存命時には長男・織田信忠の旗下にあり、信長が武田軍と対峙した甲州征伐などに従軍ました。 天正9年(1581年)の京都御馬揃えでは、信長の息子たち、信忠・信雄・信包・信孝・津田信澄の後に続いたとされ、信長御一門衆のひとりとして栄華を飾ったと... -
小野お通~信之が愛した女性~
 第2次上田合戦も終え、いよいよ九度山での蟄居生活に時代を移すことになる昌幸・信繁親子。大河・真田丸もいよいよ大詰めへ、というところでしょうか。 そして、これまでのお話しの展開の中で、スポット的に登場して視聴者を楽しませてくれた登場人物がいます。吉野太夫(初代)、出雲阿国、呂宋助左衛門(るそんすけざえもん)や、他にも清水...
第2次上田合戦も終え、いよいよ九度山での蟄居生活に時代を移すことになる昌幸・信繁親子。大河・真田丸もいよいよ大詰めへ、というところでしょうか。 そして、これまでのお話しの展開の中で、スポット的に登場して視聴者を楽しませてくれた登場人物がいます。吉野太夫(初代)、出雲阿国、呂宋助左衛門(るそんすけざえもん)や、他にも清水... -
数正息子・石川康勝のボヤ騒ぎ ~真田丸での大失策・災い転じて福となす~
 【石川数正の嫡男・康長と次男・康勝、大坂城に入城】 徳川家康の元を出奔し、豊臣方 に寝返った石川数正。関ケ原の合戦の際には数正は死去していますが、彼の死後も石川家は嫡男・康長が家督を相続、信濃・松本8万石の大名家を存続させます (※康勝も1万5千石を継承)。その後、慶長5年(1600年)の関ケ原の合戦、康長・康勝の兄弟は徳川...
【石川数正の嫡男・康長と次男・康勝、大坂城に入城】 徳川家康の元を出奔し、豊臣方 に寝返った石川数正。関ケ原の合戦の際には数正は死去していますが、彼の死後も石川家は嫡男・康長が家督を相続、信濃・松本8万石の大名家を存続させます (※康勝も1万5千石を継承)。その後、慶長5年(1600年)の関ケ原の合戦、康長・康勝の兄弟は徳川... -
島左近・清興(さこん・きよおき)
 【「三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近と佐和山の城」】 三成に三顧の礼をもって迎えられ、破格の条件で側近として仕えたという島左近。具体的にはどのような戦国武将だったのか?石田三成に仕えるまでの半生は意外にも史料が残っておらずはっきりとしていません。 まずはその出身地が不明なだけでなく、破格の条件のものとなった左近...
【「三成に過ぎたるものが二つあり、島の左近と佐和山の城」】 三成に三顧の礼をもって迎えられ、破格の条件で側近として仕えたという島左近。具体的にはどのような戦国武将だったのか?石田三成に仕えるまでの半生は意外にも史料が残っておらずはっきりとしていません。 まずはその出身地が不明なだけでなく、破格の条件のものとなった左近... -
長束正家(なつかまさいえ・ながつかまさいえ)
 【没落した自家を算術の能力で復興させた行政官】 豊臣政権下、五奉行の一人にも数えられた長束正家。父は水口盛里といわれ、元は水口城を居城とする水口を名乗った家系に生まれましたが、水口城が落城したため長束村に居住。正家は長束を名乗るようになります。 後に豪商となるような近江商人を数多く輩出することになる地域で育った正家。...
【没落した自家を算術の能力で復興させた行政官】 豊臣政権下、五奉行の一人にも数えられた長束正家。父は水口盛里といわれ、元は水口城を居城とする水口を名乗った家系に生まれましたが、水口城が落城したため長束村に居住。正家は長束を名乗るようになります。 後に豪商となるような近江商人を数多く輩出することになる地域で育った正家。... -
木村重成(しげなり)
 【秀頼とは乳母兄弟の側近】 父は関白・豊臣秀次の側近だったと伝わる木村重茲(しげこれ)。文禄4年(1595年)の秀次切腹事件の後、重茲やその長男や娘も処刑されますが、その当時、まだ3歳であった重成と、秀頼の乳母を務めていた重成の母は難を逃れることが出来ました。後、重成は秀頼の小姓として召し出され、母・宮内卿局とともに、秀頼...
【秀頼とは乳母兄弟の側近】 父は関白・豊臣秀次の側近だったと伝わる木村重茲(しげこれ)。文禄4年(1595年)の秀次切腹事件の後、重茲やその長男や娘も処刑されますが、その当時、まだ3歳であった重成と、秀頼の乳母を務めていた重成の母は難を逃れることが出来ました。後、重成は秀頼の小姓として召し出され、母・宮内卿局とともに、秀頼... -
真実の上田合戦~秀忠は関ケ原に遅れたか?~
 【通説の秀忠、関ケ原遅参】 通説によると、徳川本隊を率いた秀忠は、中山道を進んだ後、家康と合流して石田三成との決戦に参戦する予定だったのが、その途上、上田城の真田昌幸に手こずったたため関ケ原の合戦に遅参。父・家康に叱責を受けたとされています。(※詳しくは投稿記事~第二次上田合戦~関ケ原に遅参させたしたたかな戦い~) こ...
【通説の秀忠、関ケ原遅参】 通説によると、徳川本隊を率いた秀忠は、中山道を進んだ後、家康と合流して石田三成との決戦に参戦する予定だったのが、その途上、上田城の真田昌幸に手こずったたため関ケ原の合戦に遅参。父・家康に叱責を受けたとされています。(※詳しくは投稿記事~第二次上田合戦~関ケ原に遅参させたしたたかな戦い~) こ... -
キリシタンの大工・吉蔵 ~フランシスコ吉~
 真田丸・第29回「異変」に、玉・細川ガラシャとともに登場する、キリシタンの大工・吉蔵。 豊臣秀吉による禁教令を受けて長崎で刑死し、殉教者として聖人に加えられた日本二十六聖人の一人である、フランシスコ吉(フランシスコきち)をモデルにした実在の人物と考えられます。 フランシスコ吉は、パブチスタ以下24名が長崎に向かうの...
真田丸・第29回「異変」に、玉・細川ガラシャとともに登場する、キリシタンの大工・吉蔵。 豊臣秀吉による禁教令を受けて長崎で刑死し、殉教者として聖人に加えられた日本二十六聖人の一人である、フランシスコ吉(フランシスコきち)をモデルにした実在の人物と考えられます。 フランシスコ吉は、パブチスタ以下24名が長崎に向かうの... -
凡庸の2代目、徳川秀忠という男
 真田丸第28回。この回は、豊臣秀次切腹事件が新説(斬新な解釈)を用いて展開する中、星野源さん演じる徳川秀忠が初登場。秀次の影に隠れて、ネットではあまり話題に上らなかったようですが、個人的にはたいへん興味深いものでした。家康に言われて、(こちらも初登場の)本多正純に深々と頭を下げる姿は、「実直に、ただひたすら父の言いつ...
真田丸第28回。この回は、豊臣秀次切腹事件が新説(斬新な解釈)を用いて展開する中、星野源さん演じる徳川秀忠が初登場。秀次の影に隠れて、ネットではあまり話題に上らなかったようですが、個人的にはたいへん興味深いものでした。家康に言われて、(こちらも初登場の)本多正純に深々と頭を下げる姿は、「実直に、ただひたすら父の言いつ... -
秀吉~天下人のその最期~
 【秀吉の付け髭。猿は自ら呼んだ?】 「身長が低く、また醜悪な容貌の持ち主で、片手には6本の指があった。目が飛び出ており、シナ人のようにヒゲが少なかった」と記したのはルイス・フロイス。当時の武将は髭を蓄えるのが習慣だったので、髭の薄い秀吉は付け髭をすることもあったと言われています。(※中国には昔から秀吉が中国出身者である...
【秀吉の付け髭。猿は自ら呼んだ?】 「身長が低く、また醜悪な容貌の持ち主で、片手には6本の指があった。目が飛び出ており、シナ人のようにヒゲが少なかった」と記したのはルイス・フロイス。当時の武将は髭を蓄えるのが習慣だったので、髭の薄い秀吉は付け髭をすることもあったと言われています。(※中国には昔から秀吉が中国出身者である... -
秀次切腹事件に連座した人々
 その数の多さにうんざりしますが、秀次の切腹事件に際して連座して処罰されたり、殉死した家臣たちの一覧です。 この中には秀次の補佐役(後見人)を任されていた前野長康などの秀吉最古参ともいえる重臣(※秀吉伝説の墨俣一夜城築城に協力)も切腹して自害した他、後に大坂の陣で真田信繁や後藤又兵衛らと大活躍する木村重成の父・重茲など...
その数の多さにうんざりしますが、秀次の切腹事件に際して連座して処罰されたり、殉死した家臣たちの一覧です。 この中には秀次の補佐役(後見人)を任されていた前野長康などの秀吉最古参ともいえる重臣(※秀吉伝説の墨俣一夜城築城に協力)も切腹して自害した他、後に大坂の陣で真田信繁や後藤又兵衛らと大活躍する木村重成の父・重茲など... -
本多正純(まさずみ)
 永禄8年(1565年)、本多正信の嫡男として生まれた正純。この時、正信は三河一向一揆に参加して徳川家康に反逆しました。その後、一揆が家康によって鎮圧されると、家中を追放されて大和の松永久秀を頼ります。(このエピソードの詳細はこちら) しかし、正純は母親と共に三河に残り、大久保忠世(大久保忠隣の父)の元で保護されました。や...
永禄8年(1565年)、本多正信の嫡男として生まれた正純。この時、正信は三河一向一揆に参加して徳川家康に反逆しました。その後、一揆が家康によって鎮圧されると、家中を追放されて大和の松永久秀を頼ります。(このエピソードの詳細はこちら) しかし、正純は母親と共に三河に残り、大久保忠世(大久保忠隣の父)の元で保護されました。や... -
菊亭晴季(はるすえ)
 【公家の中の公家(清華家の家格)の菊亭家】 菊亭家は、大臣・大将を兼ねて太政大臣になることのできる7家(久我・三条・西園寺・徳大寺・花山院・大炊御門・菊亭)のうちのひとつ。最上位の摂家に次いで、大臣家の上の序列に位置します。 また、菊亭家(きくていけ)は今出川家(いまでがわけ)ともいい、鎌倉時代末期、太政大臣・西園寺実...
【公家の中の公家(清華家の家格)の菊亭家】 菊亭家は、大臣・大将を兼ねて太政大臣になることのできる7家(久我・三条・西園寺・徳大寺・花山院・大炊御門・菊亭)のうちのひとつ。最上位の摂家に次いで、大臣家の上の序列に位置します。 また、菊亭家(きくていけ)は今出川家(いまでがわけ)ともいい、鎌倉時代末期、太政大臣・西園寺実... -
後藤又兵衛(基次)②~長政との逸話。こんなにある!不仲の理由!!~
 【後藤又兵衛、黒田長政との逸話。こんなにある!不仲の理由!!】 ●前述の城井氏との争いでは、実は長政と又兵衛は敗戦しています。その際、一揆鎮圧軍を率いていた長政は頭を丸めて父・官兵衛に詫び、それに追従して家臣も頭を丸める中、基次は従わなかったのだとか。又兵衛は悪びれる様子もなく平然と「戦に勝敗はつきもの。負け戦の度に...
【後藤又兵衛、黒田長政との逸話。こんなにある!不仲の理由!!】 ●前述の城井氏との争いでは、実は長政と又兵衛は敗戦しています。その際、一揆鎮圧軍を率いていた長政は頭を丸めて父・官兵衛に詫び、それに追従して家臣も頭を丸める中、基次は従わなかったのだとか。又兵衛は悪びれる様子もなく平然と「戦に勝敗はつきもの。負け戦の度に... -
後藤又兵衛(基次)
 黒田如水(官兵衛)、黒田長政親子に仕え、「黒田八虎」にも数えられた豪勇の戦国武将・後藤又兵衛。大河・真田丸では、哀川翔さんの配役が発表されました。黒田家を出奔して、牢人した後に、大坂の陣では豊臣方として入城。真田信繁の強力な盟友(ライバル)として、また最大の理解者として、大坂の陣での真田信繁を物語るときには、必要不可...
黒田如水(官兵衛)、黒田長政親子に仕え、「黒田八虎」にも数えられた豪勇の戦国武将・後藤又兵衛。大河・真田丸では、哀川翔さんの配役が発表されました。黒田家を出奔して、牢人した後に、大坂の陣では豊臣方として入城。真田信繁の強力な盟友(ライバル)として、また最大の理解者として、大坂の陣での真田信繁を物語るときには、必要不可... -
長宗我部盛親(もりちか)
 大河ドラマ『真田丸』、大坂の陣に欠かせない3人が決定! 大野治長役は今井朋彦さん、明石全登役は小林顕作さんの他、長宗我部盛親役は阿南健治さんに決まりました。 陣中、牢人衆の中では最大勢力を有したといわれる長宗我部盛親。その人物像に迫りたいと思います。 【その生い立ちと、嫡子になるまで】 天正3年(1575年)、四国の...
大河ドラマ『真田丸』、大坂の陣に欠かせない3人が決定! 大野治長役は今井朋彦さん、明石全登役は小林顕作さんの他、長宗我部盛親役は阿南健治さんに決まりました。 陣中、牢人衆の中では最大勢力を有したといわれる長宗我部盛親。その人物像に迫りたいと思います。 【その生い立ちと、嫡子になるまで】 天正3年(1575年)、四国の... -
明石全登(たけのり・ジュスト)
 【謎多き戦国の武将・明石全登】 播磨を支配した名門・赤松氏の支流にあたるとも言われる備前明石家。明石行雄(※景親とも)の子として生まれたとされる明石全登ですが、実際のところ、その生年や、全登という文字の正しい読みなど不明な点の多い人物。キリシタンであったとされています。(※全登は、たけのり、おしとう、ぜんとう、てるずみ...
【謎多き戦国の武将・明石全登】 播磨を支配した名門・赤松氏の支流にあたるとも言われる備前明石家。明石行雄(※景親とも)の子として生まれたとされる明石全登ですが、実際のところ、その生年や、全登という文字の正しい読みなど不明な点の多い人物。キリシタンであったとされています。(※全登は、たけのり、おしとう、ぜんとう、てるずみ... -
伊達政宗~その半生と野望・秀吉臣従まで~
 【コンプレックスに悩んだ少年時代】 永禄10(1567)年、父・輝宗と母・義姫(保春院)の間に、伊達家の嫡男として米沢城に生まれたとされる政宗。幼名は梵天丸と言いました。 4歳(※諸説あり)のころに天然痘を患ったせいで右目を失明。そんなこともあってか、幼少のころは気弱な性格であったと伝わっています。 そして、政宗が8歳のころに...
【コンプレックスに悩んだ少年時代】 永禄10(1567)年、父・輝宗と母・義姫(保春院)の間に、伊達家の嫡男として米沢城に生まれたとされる政宗。幼名は梵天丸と言いました。 4歳(※諸説あり)のころに天然痘を患ったせいで右目を失明。そんなこともあってか、幼少のころは気弱な性格であったと伝わっています。 そして、政宗が8歳のころに... -
豊臣秀次と秀勝、秀保。その父・弥助。
 叔父・秀吉が出世、天下人となったことでその運命を翻弄された兄弟とその父親。かれらの人生とはどのようなものだったのでしょうか。 【父・木下弥助(三好吉房)】 秀吉(木下藤吉郎)の姉・とも(瑞龍院・日秀尼)を妻として、その間に秀次、秀勝、秀保をもうけました。弥助の出自については諸説あり(というか記録が残っていない)...
叔父・秀吉が出世、天下人となったことでその運命を翻弄された兄弟とその父親。かれらの人生とはどのようなものだったのでしょうか。 【父・木下弥助(三好吉房)】 秀吉(木下藤吉郎)の姉・とも(瑞龍院・日秀尼)を妻として、その間に秀次、秀勝、秀保をもうけました。弥助の出自については諸説あり(というか記録が残っていない)... -
宇喜多秀家
 元ジャニーズの高橋和也さん演じる、宇喜多秀家。同じく岡本健一さん演じる、毛利勝永も配役が発表されており、中年世代には懐かしい「男闘呼組」の共演が地味に実現しています。(岡本健一さんは現在もジャニーズ事務所・所属)。真田丸での宇喜多秀家は、どんな些細なこともおろそかにしない、熱血漢。「大坂城の松岡修造」となるらしく、...
元ジャニーズの高橋和也さん演じる、宇喜多秀家。同じく岡本健一さん演じる、毛利勝永も配役が発表されており、中年世代には懐かしい「男闘呼組」の共演が地味に実現しています。(岡本健一さんは現在もジャニーズ事務所・所属)。真田丸での宇喜多秀家は、どんな些細なこともおろそかにしない、熱血漢。「大坂城の松岡修造」となるらしく、... -
毛利勝永
 【牢人五人衆のうちのひとり、毛利勝永】 大河「真田丸」では岡本健一さん演じる毛利勝永。(今回の大河では初のジャニーズ登場?)大坂城に入城した牢人(浪人)のうち、元大名、もしくは大名格のものを「大坂五人衆」と呼び、勝永はその中の一人にあたります。 ※余談ですが、浪人(ろうにん)はもともと、戸籍に登録された地を離れて他国を...
【牢人五人衆のうちのひとり、毛利勝永】 大河「真田丸」では岡本健一さん演じる毛利勝永。(今回の大河では初のジャニーズ登場?)大坂城に入城した牢人(浪人)のうち、元大名、もしくは大名格のものを「大坂五人衆」と呼び、勝永はその中の一人にあたります。 ※余談ですが、浪人(ろうにん)はもともと、戸籍に登録された地を離れて他国を... -
片倉景綱(小十郎)
 伊達政宗の近習となり、のち軍師的役割を務めたとされる伊達家の重臣。景綱の姉、喜多は政宗の「乳母」を務めた人物。 片倉景綱の通称「小十郎」は、景綱に始まる仙台藩・片倉氏の代々の当主が踏襲して名乗る名称です。 【政宗の軍師・片倉小十郎景綱】 景綱が参戦した合戦には、 天正13(1585)年 人取橋の戦い 天正16(1588)年 ...
伊達政宗の近習となり、のち軍師的役割を務めたとされる伊達家の重臣。景綱の姉、喜多は政宗の「乳母」を務めた人物。 片倉景綱の通称「小十郎」は、景綱に始まる仙台藩・片倉氏の代々の当主が踏襲して名乗る名称です。 【政宗の軍師・片倉小十郎景綱】 景綱が参戦した合戦には、 天正13(1585)年 人取橋の戦い 天正16(1588)年 ... -
千利休、切腹の謎
 切腹を命じにきた秀吉の使者に対して、全く動じず利休は静かに口を開いて言ったといいます。 【「茶室にて茶の支度が出来ております」。】 しかし、切腹を命じられた真相については諸説あり、本当のところはわかっていません。 一般的に言われている説には、 ● 秀吉が利休の娘に近待するよう要求したが拒否されたという説 ● 利休が...
切腹を命じにきた秀吉の使者に対して、全く動じず利休は静かに口を開いて言ったといいます。 【「茶室にて茶の支度が出来ております」。】 しかし、切腹を命じられた真相については諸説あり、本当のところはわかっていません。 一般的に言われている説には、 ● 秀吉が利休の娘に近待するよう要求したが拒否されたという説 ● 利休が...