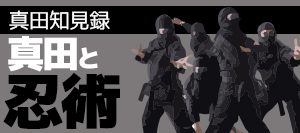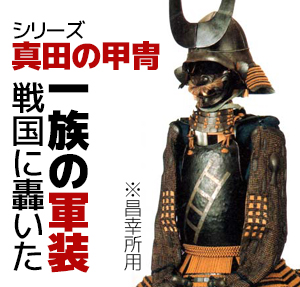学校の授業で歴史を学ぶ際、そこに登場する事象の裏で、どのような激情が渦巻いていたのかまで教わることはほぼない。しかし、歴史というものは、ひとりひとり人間が抱いた愛憎の感情が少なからず影響を及ぼしているのだ。今回は平安時代の婚姻スタイルが、政治を変えた話をお届けする。『愛憎の日本史』 (扶桑社新書) より、一部抜粋、再構成してお届けする。 『愛憎の日本史』#2 #1 平安時代の婚姻スタイル・「招婿婚(しょうせいこん)」とは何か 恋愛が重視された平安時代。当時の婚姻制度とはどんなものだったのでしょうか。 エマニュエル・トッド氏(フランスの家族人類学者・歴史学者)の理論でいうと、持統天皇の時代以降、日本の天皇家をはじめとする家族形態は、「単婚小家族」という父・母・子というシンプルな形態から、一人の子どもが親の財産をすべて受け継ぐ「直系家族」と呼ばれる家族形態へと移行していきます。 家族形態が変わるといっても、一代、二代で変わるものではありません。その過渡期に登場した婚姻形態が、平安時代の「招婿婚」だと考えます。 「嫁入り」という言葉に代表されるように、日本では最近まで女性が男性の家に嫁に行く「嫁取婚(よめとりこん)」が根付いていました。一方の招婿婚は、男性が女性のもとに通う婚姻スタイルです。ときには、「妻問婚(つまどいこん)」とも呼ばれます。 招婿婚を提唱したのが、高群逸枝先生です。高群先生は『招婿婚の研究』という本の中で、平安時代の結婚の内情を明らかにされています。同著によれば、平安時代の結婚の成り立ちは以下の通りです。 まず、「この家には素敵な女性がいるらしい」との噂を聞きつけた男性が、その女性に歌を贈ります。仮にその歌が女性の心を動かせば、女性は男性に返歌を贈る。 男女の間で和歌のやり取りが数回行われた後、男性が求愛します。そのとき、女性から「うちに遊びにいらっしゃい」という誘いがあれば、男性が女性の家に忍んでいき、関係を持ちます。 なお、昔の身分の高い女性はだいたい扇で顔を隠しているので、直接会って事前に顔を確かめることはできませんでした。平安時代の恋人同士は契りを交わす段階で、初めてお互いの顔を確認する。ときにはお互いに「……こんな顔だとは思わなかったのに!」と悲鳴が上がることもあったかもしれません。 招婿婚は基本的には女性やその両親がリードして成立する婚姻スタイルなのに… でも、一度関係を持ったからといっても、婚姻関係には至りません。二人で一夜を明かした後もお付き合いが続き、女性が「この人は特別に良いな」と思った際に、ようやく女性側の両親が登場します。 女性が両親に「この人が私の選んだ人です」と男性を紹介し、男性も「お嬢さんとお付き合いさせていただいております。どうぞよろしくお願いします」と挨拶をする。 この「露顕(ところあらわ)し」という儀式を経て、両親が「この男は良い男だな。よし、うちの娘の婿として認めてやろう」と考えれば、婚姻は成立します。 両親との顔合わせも済んだ後であれば、男性は夜に限らず、時間帯を選ばずに女性の家に通うことができました。仮に二人の間に子どもができたら、母方の祖父母、すなわち女性の両親の家で育てるのが一般的で、その子が成長すると、母方の家の財産を相続することができました。 ここでポイントなのは、招婿婚とは、基本的には女性やその両親がリードして成立する婚姻スタイルだったという点です。また、女性の家で子どもが育つということは、祖母から母へ、母から娘へ……と女系の血筋で家がつながることを意味しています。これらは、当時の女性の存在感が社会的にも大きかったことの証左でしょう。 ですが、ここでひとつ疑問が浮かびます。仮に女性の血筋で家がつながっていたのであれば、当時の家系図も女性の系図で残されてもおかしくない。 しかし、この時代の家系図を見ると、天皇家はもちろん、藤原氏や大伴氏もやはり男性の系図しか見当たりません。家自体は女性の間でつながっていくのに、家系図は男性でつながっている。これは、非常にいびつで、不完全な状態です。 この不完全さがあったからこそ、家族形態として招婿婚は定着せず、平安時代を過ぎると、現代の私たちが知るような、祖父から父へ、父から息子へ、息子から孫へと男系で代々の家が続いていったのではないでしょうか。 トッド氏の理論を援用すれば、おそらく単婚小家族から直系家族へと日本の家族形態が移行するひと時に、男性が女性の家に通うという婚姻スタイルが発生しました。 大きな歴史の流れのなかで、家族形態のようなものが変化するのにはそれ相応の時間がかかります。 事実、その後招婿婚は150〜200年ほど続きました。その後、その中の一人の子どもが全ての財産を受け継ぐ直系家族へと移行していきます。 こうして、大きな歴史の過渡期に生まれた〝バグ〞であった招婿婚は、日本の歴史から姿を消した。僕はそう考えています。 婚姻形態と政治が結びつき、その結果、日本の歴史が変わった 「招婿婚」から「嫁取婚」への婚姻形態の移行は、政治にも大きな影響を与えます。 すでにご説明したように、招婿婚の時代に行われた摂関政治は、天皇の母方の祖父が権力を握る形態でした。繰り返しになりますが、招婿婚は女性側が主導権を持つ婚姻スタイルです。 まさに天皇の母方の家族、すなわち外戚が主導権を持つ摂関政治は、招婿婚の中で母方の政治発言力が高まった末に生まれたものだったのでしょう。 しかし、家族形態が直系家族へと変化し、婚姻制度が招婿婚から嫁取婚へと変化し、母方の存在感が弱まるうちに、摂関政治も力を失っていったのでしょう。もっとも、これは卵が先か、鶏が先かという理論と同じく、婚姻形態が変わったから政治構造が変わったのか、はたまた政治権力の構造が変わったから婚姻形態も変化したのか、その因果関係はわかりません。 しかし、婚姻形態と政治が結びつき、その結果、日本の歴史が変わったことには間違いないでしょう。 女性が主導権を持つ招婿婚から男性が主導権を持つ嫁取婚へと婚姻形態が変わりつつあった頃、天皇の母方の祖父が権力を握る摂関政治から、天皇の父方の祖父や父などの尊属が権力を持つ院政へと移り変わっていきました。 摂関政治の不安定さで、藤原氏は没落していった なぜ政治形態が変わっていったのか。 大きな理由のひとつは、摂関政治の不安定さにあったのではないかと僕は考えます。先にも述べたように、摂関政治は娘が生まれ、なおかつその娘が天皇の子どもを身ごもることで完成するもの。非常に偶然性に左右されやすい脆弱な政治形態です。 事実、藤原氏は平安時代の後期になると急速に力を失っていきますが、その原因となったのは「次期天皇が生まれなかったから」なのです。 藤原道長といえば、「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたることも なしと思へば」という有名な歌にあるように、摂関政治の最盛期を築いた人物です。 その栄華は、宇治の平等院鳳凰堂を建てた、道長の息子・頼通の時代までなんとか続きました。しかし、この頼通の晩年近くに台頭するのが、天皇の父や祖父が権力を握る「院政」でした。 院政が始まるきっかけとなったのは、皇族の両親を持つ後三条天皇の存在です。 平安時代の歴代の天皇は、藤原氏の母親を持つことが一般的でした。しかし、後三条天皇は、約二百年ぶりに藤原氏を母親に持たない天皇として即位しました。 皇族の血が強い天皇が即位すれば、当然藤原氏の権力は弱体化します。 にもかかわらず、なぜ藤原氏は後三条天皇の即位を阻止できなかったのかといえば、藤原氏の血を引く天皇家の男児が生まれなかったからです。 まさに、摂関政治が偶然性に頼り過ぎていて、非常に脆弱な政治構造だったからこそ、起こった出来事だと言えます。 […]
現代ではありえない、婚姻形態が政治を変えた平安時代。日本の歴史からやがて消えた、男性が女性のもとに通う婚姻スタイル「招婿婚(しょうせいこん)」とは?