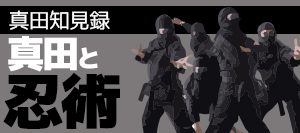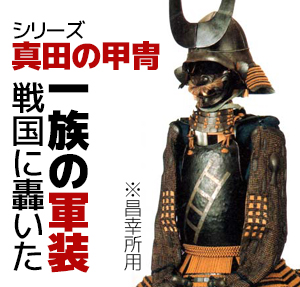日本で最初にセーラー服を着用した学校はどこか。日本大学商学部准教授で歴史学者の刑部芳則(おさかべ・よしのり)さんは、旧制の高等女学校(現在、その多くは新制高校に継承)の記録など膨大な史料にあたって検証し、セーラー服の起源校を明らかにした。刑部さんは新刊『セーラー服の誕生』(法政大学出版局)のなかで、その研究成果をまとめている。刑部さんに話を聞いた。 ―――なぜ、セーラー服の起源を調べようと思ったのでしょうか。 セーラー服の起源をめぐっては、さまざまな説が取り沙汰されていました。しかし、どれもデータが乏しいなど信用できなかった。わたしは歴史学者としてしっかり調査しようと思ったわけです。たとえば、2000年代半ばまで福岡女学院(福岡女学院中学校・高校)の「セーラー服を最初に制定」が長い間、定説になっていました。ところが、2007年、制服販売会社の研究室長が平安女学院(京都、平安女学院中学校・高校)が起源という説を発表します。これによって、福岡女学院は1921(大正10)年12月、平安女学院は1920(大正9)年11月にセーラー服を制定ということになりました。 ―――当時、メディアは平安女学院が1年以上早く日本で最初のセーラー服校と伝えています。どっちが先か、ちょっとした論争になりました。 わたしは「セーラー服邪馬台国論争」と呼んでいます。 ―――実際、どうなのでしょうか。 福岡女学院は上下分かれたセパレート、平安女学院はワンピースタイプでした。制服販売会社の研究室長はセーラー服の元祖はセパレートならば福岡女学院、ワンピースならば平安女学院と2通りあるような見解を示したわけです。セーラー服を定義しなかったので、起源はどっちつかずで、いい加減な話になったのです。それがメディアで語り継がれるわけですが、これではだめでしょう。セーラー服の起源が二つあるという見方はおかしい。極端な話、日本で最初の幕府は鎌倉、室町、江戸と何通りもできてしまう。また。この研究室長は約15校を調査したとありますが、いくらなんでも少なすぎます。残念なことに、制服を研究している学者のなかにこの説を信じる者がいます。わたしは歴史学者として看過できませんでした。 ■「セーラー服邪馬台国論争」に決着 ―――そこで、刑部さんは何から取り組んだのでしょうか。 セーラー服邪馬台国論争を終わらせなければならない。そのためにセーラー服をしっかり定義することからはじめました。日本にセーラー服が入ってきたのは幕末のことです。幕府の海軍がイギリスの海軍水兵のセーラー服姿を見て採り入れました。水兵のセーラー服はセパレート型で上下分かれているので脱ぎやすく機能的です。したがって、ワンピース型はセーラー服とはいえない。平安女学院の起源説はなくなります。実際、ワンピース型は他校でまったく見られませんでした。 ―――すると、セーラー服起源校はどこになるのでしょう。福岡女学院ですか。 いや違います。わたしは北海道から沖縄まで全国に900以上存在した高等女学校の制服を調べてみました。すると、福岡女学院よりも早くセーラー服を着用した可能性がある高等女学校がいくつか見つかったのです。そのなかでもっとも有力なのが、金城女学校(愛知、現・金城学院高校)でした。1921(大正10)年9月にセーラー服が制定されており、女子生徒の集合写真が残っています。金城女学校がセーラー服の起源であることに疑問の余地はありませんでした。 ―――セーラー服邪馬台国論争はどうなりましたか。 最近、話題になりません。平安女学院、福岡女学院の名前は出なくなり、金城女学校がセーラー服の元祖ということが定着しています。ただし、2022年3月、京都の地元紙でセーラー服が廃止されたと報じられましたが、「日本で初めてセーラー服を学校制服に採用したのは京都市上京区の平安高等女学校(現平安女学院)とされる。1920年に、はかまから洋式制服に代わった。ウエストにベルトが付いた紺色のワンピースで、大きな襟が特徴だった」とわざわざ写真付きで紹介されていました。メディアとしてまったく検証していない。いかがなものかと思います。残念でなりません。 ―――そもそも、なぜ高等女学校はセーラー服を採り入れたのでしょうか。 明治時代に入って全国に高等女学校が誕生します。はじめのころ通学服は着物とはかまでした。大きな契機になったのは、1919(大正8)年に起こった服装改善運動です。未成年には洋式の服装を着せようという動きです。洋服は、着物とはかまに比べ経済的で体を縛らず機能性があり、多くの人に受け入れられました。それは高等女学校の制服にも大きな影響を与えます。ここでセーラー服、ブレザー、ジャンパースカートの制服が誕生しました。日本で最初に洋式の制服が採り入れられたのは、山脇高等女学校(東京、現・山脇学園高校)です。大正8年のことです。セーラー服については、女子生徒からかわいらしいデザインだと人気があり、支持されます。学校が着せたというより、生徒が好んで着るようになりました。 ■セーラー服と関東大震災の関係は? ―――セーラー服の誕生の背景に関東大震災説がありました。これは、どうなのでしょう 。 関東大震災のとき和服ゆえ逃げ遅れた者が多かった反省から、洋服が採り入れられセーラー服が普及したという説があります。この立場をとる服飾史の研究者がいます。ですが、これは間違いです。それ以前に洋装化が広がったことによります。 もう一つ、大きな理由があります。当時、「バスガール」と呼ばれたバスの女性車掌が着る制服が、高等女学校の制服に似ていました。生徒たちはバスガールに間違われることがあり、彼女たちはそれを好ましく思わなかった。バスガールに間違われないよう、セーラー服を望んでいたようです。これには多くの証言が残っています。当時、高等女学校の生徒はバスガールという職業を軽視するほどエリート意識があったのでしょう。 ―――同じセーラー服でも私立、公立による違いはあったのでしょうか。 私立のほうが自由度は尊重されて発想が豊かでした。デザインはシンプルなものでなく創意工夫がなされています。襟にしるされた線の数が多かったり、線に色彩が付けられたり、スカーフがカラフルだったり、かなり特徴的でした。高等女学校の先生が出張で他府県を訪問したとき、他校の制服に魅了されて、自分の学校に採り入れたケースもあります。北陸女学校(石川、現・北陸学院高校)の事務長が横浜を訪れた際、横浜共立女学校(現・横浜共立学園高校)の制服がかっこいいと思い、同校の制服と同じように変えてしまったということもあります。いまでも両校の制服がよく似ていることはウェブサイトで確認できます。公立のほうが斬新さは見られず、シンプルなデザインです。 ―――第2次大戦中はどうだったのでしょうか。 戦争が激しくなると、スカートは禁じられ、ヘチマ襟、ズボン、モンペ姿が見られるようになります。1941(昭和16)年、文部省は標準服を制定します。セーラー襟を廃止し、ヘチマ襟になります。評判は良くなかったようです。しかしセーラー服が消えることはなく、たとえば、1944(昭和19)年、東京府立第五高等女学校(現・都立富士高校)の卒業写真は全員セーラー服姿でした。もっとも、地域によってはバラツキが見られ、標準服のほうが多い学校も少なくなかったようです。 ■戦後、ブレザーに変わる動きが起きた理由は ―――戦後、高等女学校はいまの新制高校に変わります。セーラー服は残ったのでしょうか。 浦和第一高等女学校は浦和第一女子高校(埼玉)に、千葉高等女学校は千葉女子高校になったとき、セーラー服からブレザーに変わりました。進学校で有名な桜蔭中学・高校も、前身の桜蔭高等女学校から変わるとき、セーラー服をやめてブレザーになりました。セーラー服を廃止した学校のなかには、軍服をイメージさせる、軍国主義の名残である、という理由を示したところもあります。戦争に負けて大日本帝国から日本国に変わったことで、前時代のものが全否定され、そのなかにはセーラー服も入っていたということでしょう。しかし、これは歴史的事実を無視した主張です。戦争中のモンペ姿のほうが軍国主義的だった、セーラー服は平和な時代の象徴だったと振り返る生徒もいました」 ―――いまでもセーラー服の伝統を守っている学校があります。 有名なのが学習院女子中・高等科(東京、旧・女子学習院)、東京女学館中学校・高校(旧・東京女学館)、フェリス女学院中学・高校(神奈川、旧・フェリス和英女学校)などです。いわゆる伝統校であり、ブランド意識を強く持っており、制服を変えようという考えはまったくありません。祖祖母のころからこうした学校に通い、4代続けて同じセーラー服を着ている家系もあります。誇りを持って着続けてほしいです。セーラー服をやめてしまった学校も、「後世に伝える」という意味で、復刻ブランドを立ち上げるのもいいかもしれません。 <フェリス女学院のウェブサイトに以下の記述。 「セーラー服がフェリス女学院の標準服として着用が推奨されたのは、1921(大正10)年のことです。関東大震災後に制服として正式決定され全員が着用するようになりました。冬服は紺のセーラーカラーにひだスカート、襟のライン、ネクタイはえんじ。夏服は白地の上着にブルーグレーのギンガム地のセーラーカラー、襟のラインは白、黒のネクタイ。スカート丈、ネクタイの結び方などは、その時代その時代で多少変化はしているものの、今日まで100年ほぼ変わることなく大切に着続けられています」> ―――刑部さんはそれだけ学生服への思いが強くあるようですが、いつごろから興味を持たれたのでしょうか。 子どものころから学ラン、セーラー服が好きでした。中学1年生の登校初日、わたしの学校は男女ともにブレザーでしたが、線路の向こう側にある学校が学ランとセーラー服だったのです。その姿がとてもうらやましく、いつかは 学ラン、セーラー服の歴史を解明したいと思っていました。 ―――学生服について、これから取り組まれるテーマについて教えてください。 学ラン、セーラー服が姿を消しつつあります。それがなぜなのか。戦後から今日に至るまで、女子のセーラー服、男子の学ランに対する意識を調べて、学生服の歴史をしっかり検証したい、と考えています。 (構成/教育ジャーナリスト・小林哲夫) 刑部芳則(おさかべ・よしのり)/日本大学商学部准教授。1977年東京都生まれ。中央大学大学院博士後期課程修了、博士(史学)。著書に『古関裕而』(中公新書)、『帝国日本の大礼服』(法政大学出版局)、『三条実美』(吉川弘文館)など。NHK連続テレビ小説「エール」の風俗考証などを担当。 もっと記事を見る
日本で初めてセーラー服を着用した学校は? 歴史学者が明らかにしたセーラー服の100年