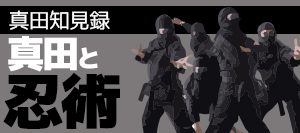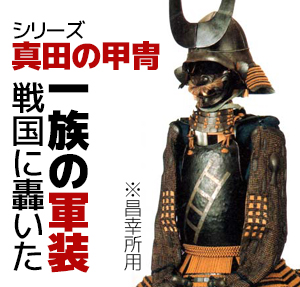真田丸、本多正信を通して描かれる、新しい「家康像」
大河・真田丸に登場する徳川家康(内野聖陽)。後に天下人となる彼のもとには、たいへん有能で個性的な戦国武将が数多く存在します。もちろんドラマではその全員を取り上げるわけにもいかない訳ですから、原作なり、脚本なりでの中で、重要人物をどのように描いていくか?で、その周辺人物のピックアップも変化していきます。
今回の「真田丸」で三谷幸喜さんが重点を置く徳川重臣はこの三人。
・本多忠勝(藤岡弘、)・・・弘の後に「、」最近気が付きました…
・本多正信(近藤正臣)
後に秀吉からヘッドハンティングを受け、家康のもとを離れる石川数正は、ドラマの中での役割は「数正個人」にフューチャーされていると読めますが、忠勝vs正信に関しては、まさにその「対比」を際立たせることによる、新しい徳川家康像の構築を感じることが出来ます。
実際、本多正信が徳川家で活躍するのは、忠勝のような「槍働き」ではなく、知略や謀略を多用した家康の天下統一事業が成される後半に、その参謀としてです。ドラマの早い段階からの頻出は、真田丸での重要なポストを示唆していると言えます。
一時は「乱世の梟雄」と呼ばれた松永久秀にも仕えた、家康の参謀
初めは鷹匠として家康の側近近くに仕えた正信。その才能を買われて徐々に重用されるようになります。ですが永禄六年(1563年)三河一向一揆が起こると一揆側の武将として家康に敵対(忠勝は家康側)。やがて一揆が家康側に鎮圧されると徳川家を出奔して、あの松永久秀に仕えます。
※松永久秀・・・乱世の梟雄(きょうゆう。残忍で強い人の意味)。久秀は、信長を3回も裏切ったのにもかかわらず、それを許されたました。また、日本で初めて爆死した人物でもあります。
久秀の元を去った後、諸国を放浪していたとされ、家康のもとに帰参するまでの動向は不明(石山本願寺で織田信長と戦ったなどの説あり。)。遅くても本能寺の変のころには、再び徳川に仕えたとされています。
松永久秀からの影響も少なからずあったでしょうし、また、この時期の激動する情勢も正信の価値観に変化を与えたと思われます。
慶長3年(1598年)、秀吉が死去すると、いよいよ正信は表舞台へ。この頃から家康の参謀として大いに活躍するようになり、家康が覇権奪取を行なう過程で行なわれた慶長4年(1599年)の前田利長の謀反嫌疑の謀略など、家康が行なった謀略の大半は、この正信の献策によるものであったと言われています。
家康からの厚い重用、「友」とさえ呼ばれた家臣・本多正信
徳川家のその他の家臣達からは評判が相当に悪く、嫌われていた正信。重臣・榊原康政からは「腸の腐った奴」。また、一族の本多忠勝からは「正信の腰抜け」、「同じ本多一族でもあやつとは全く無関係である」などさんざんな言われようです。
しかし、家康の信任は相当に厚かったようで、「家康の寝室に帯刀していても自由に出入りを許された。」や、「正信が何を言っているのか第三者には理解できなくても、家康は理解できた。」など、まさに以心伝心で、常人には理解できないような関係性が見て取れます。
そして、1616年4月に家康が死去すると、正信はすぐに嫡男・正純に家督を譲り隠居。それからわずか2ヵ月後、79歳で正信は亡くなります。
晩年は権力闘争に明け暮れた正信ですが、彼の石高は2万石とも一説には1万石とも言われて、すごく少ない?印象で、イメージにそぐわない人物像も見て取れるのです。
ひょっとすると権力欲があるというよりも、主君が目指す目的を果たすため、その障壁となるものは如何なる手段を用いてでも排除したいという気持で行動していたのではないでしょうか。
戦乱の世を太平に導き、後に300年に渡る安定政権。そんな世の中を創造することが家康の目的だったとして、その家康から友人のような扱いを受けた正信も同じ大望を持っていたのかも知れません。
そんなビッグな人物だったのなら、周囲からひどく嫌われても何とも思っていなかったと推測できますね。知れば知るほど、魅力的な人物なのです。
おそらく真田丸では、既存の正信のパブリックイメージ「頭が良くて嫌なやつ」で展開されると思われますが、こういった彼の一面を知っておくとまた面白いかもしれません。
ちなみにですが、2011年の大河ドラマ、江〜姫たちの戦国〜で、この本多正信を演じたのは草刈正雄さんでした。みなさま覚えておられましたか?